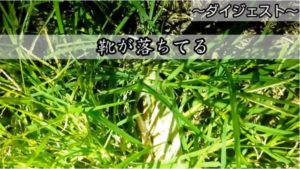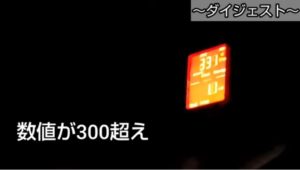Contents
本題
視聴者リクエストで、関東にある某田んぼ沿いを訪れた。
到着直後から不穏な空気漂う場所で幽霊達は何を見たのか。
| 【使うもの】 ①声まね人形 ②歩く人形 ③磨りガラス |
※動く人形の描写や、影や音の描写は最小限にして発言を記載します。
※視聴者イラストも著作、肖像権の観点から掲載を省きます。
感想
■あの田んぼ沿いで何がありましたか?








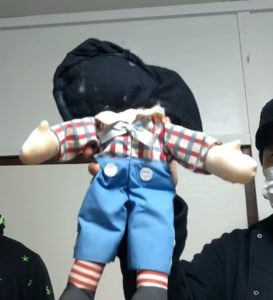
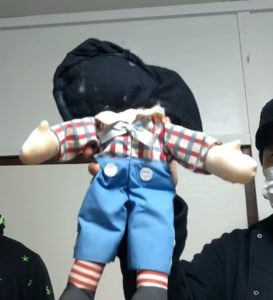
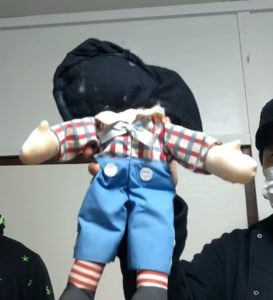
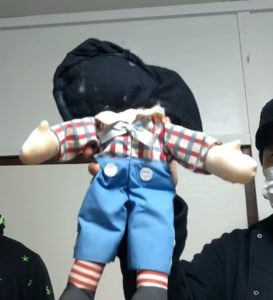
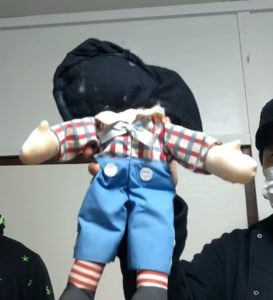




今回はここまで
” 神楽鈴 ”
神楽鈴・巫女鈴の豆知識
https://odori-company.com/?mode=grp&gid=1999606
神楽鈴は巫女が神楽舞(巫女舞)を舞う時に持つ鈴です。
神楽(かぐら)とは、「神座」(かむくら・かみくら)が転じたとされる言葉で「神の宿るところ」「招魂・鎮魂を行う場所」を意味し、そこでの歌舞が神楽と呼ばれるようになったとされるそうです。
元来、鈴には魔除け、神様を呼ぶ効果があると言われ、神社の参拝時に鳴らす鈴にも同じ意味があります。
また、この鈴は能楽や歌舞伎などで『三番叟(さんばそう)』を踊るときにも使用されますので三番叟鈴(さんばそうすず)とも言います。
三番叟とは神事儀礼の舞曲の一つで五穀豊穣、延命長寿、子孫繁栄を祈り、この鈴を持って踊ります。
神楽鈴の鈴は三段の輪状に付けられ、下から七個、五個、三個になっており、別名七五三鈴とも呼ばれております。
七五三と言うと子供の成長を祝う『七五三詣』が思い浮かびますが、古来中国の縁起の良い数字「奇数」に起因すると言われています。
また、この七五三の数字に因むものが神社にはもう一つあります。
それは神社の鳥居に付けられている注連縄(しめなわ)で注連縄の藁を、七束、五束、三束と垂らす型があり、しめなわは七五三縄とも書きます。
他にも果実がたくさん実を付けることを形容して『鈴なり』と言いますが、神楽鈴の鈴のつき方と似ているのでこの言葉が生まれました。
七五三詣でとつながっていたり言葉の語源になったり、神楽鈴は昔から日本人にはなくてはならない小道具の一つとなっております。